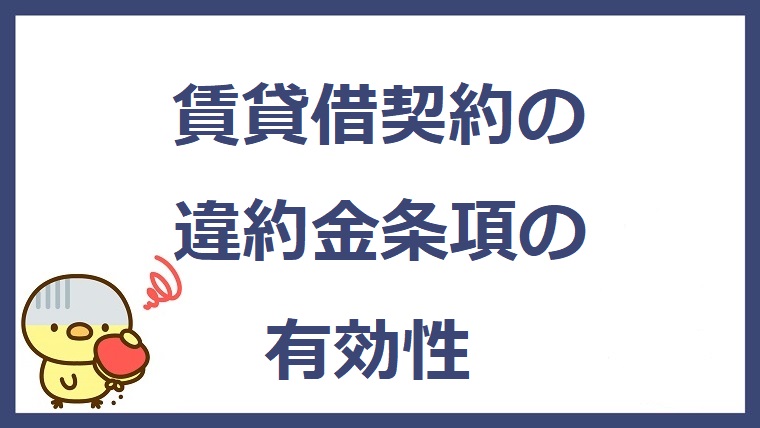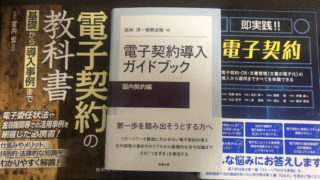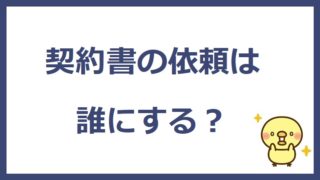商業施設等でのテナントの賃貸借契約で、契約期間の定めがある場合、中途解約時には残存期間の賃料相当額を違約金として貸主が借主に請求できるといった条項がある場合があります。
この記事では、そのような違約金条項の有効性について弁護士が解説しています。
賃料1年分を超える部分の違約金は無効となる可能性が高い
例えば、賃料1ヶ月40万円、5年間を契約期間として定めた賃貸借契約で、1年間満了時に中途解約をしたいとします。
この場合、残存期間の賃料相当額を違約金として支払わなければならない条項があるとすると1920万円もの違約金が発生することになります。
40万円×12ヶ月×4年=1920万円
しかしながら、貸主は明渡後にはあらたな借主を見つけてテナントを貸すことができるわけで、残存期間全部の賃料相当額を違約金として請求できるというのは素人目にみても暴利行為といえそうです。
この点については、裁判例の動向から賃料相当額1年分程度については有効とされ、1年分を超える部分は無効とされる可能性が高いといえます。
違約金に関する裁判例
では、実際にこのような違約金条項の有効性が問題となった裁判例を紹介します。
事案の概要(東京地判平成8年8月22日)
契約期間4年間でのテナントの賃貸借契約において、「借主が期間満了前に解約する場合は、解約予告日の翌日より期間満了日までの賃料・共益費相当額を違約金として支払う。」との合意があった、借主が約10か月で解約したため、貸主は約3年2ヶ月分の賃料等相当額を請求した。
この事案において、東京地裁は次のとおり述べ、1年分の賃料等を超える部分の違約金を公序良俗に反して無効と判断しました。
判旨(東京地判平成8年8月22日)
以上の事実によると、解約に至った原因が被告会社側にあること、被告会社に有利な異例の契約内容になっている部分があることを考慮しても、約三年二か月分の賃料及び共益費相当額の違約金が請求可能な約定は、賃借人である被告会社に著しく不利であり、賃借人の解約の自由を極端に制約することになるから、その効力を全面的に認めることはできず、平成六年三月五日から一年分の賃料及び共益費相当額の限度で有効であり、その余の部分は公序良俗に反して無効と解する。
また、コーヒー店を営むためにテナントを10年間の定期建物賃貸借契約を締結し、賃借していた賃借人の事例である東京地判平成17年2月21日を紹介します。
この事例では、以下のような条項がありましたが、賃借人は、6ヶ月を超える部分の違約金は無効であるとして、敷金から1年間分の賃料相当額の違約金のうち6ヶ月分の返還を求めた事案です。
問題となった条項
賃貸人又は賃借人は、12か月前までに相手方に対し書面により本契約の解約を予告することによって、本契約を解約することができる。なお、賃借人は、予告に代えて12か月分の賃料相当額(解約金)を賃貸人に支払い即時に解約することができる。
これについて、東京地判は、次のように述べ、1年間分の賃料相当額を違約金とする条項を有効と判断しました。
判旨(東京地判平成17年2月21日)
本件契約における解約予告条項は、本件ビルのテナント契約が10年間の定期建物賃貸借契約とされ、中途解約を認めないことの特約として相当性のあるものと認められ、上記契約期間中の解約による新テナント募集及び設備・内装工事等に要する時間、費用等を考えれば、12か月という期間も、長期に過ぎて不当であるとも認められず、12か月分の賃料相当額の解約金の約定が、暴利で、公序良俗に反するとまでは認められない。本件契約の特約としての解約予告条項は、被告の希望、選択により採用されたものであり、この場合においても、被告が当然に12か月分の賃料相当額の解約金の支払を負担するものではなく、12か月の期間をおいて解約予告をするか、これに代えて上記解約金を支払うかを被告において選択し得るものであるから、契約自由の原則に照らしても,自由経済の原理に反するものではなく、上記解約予告条項をもって公序良俗に反するとはいえないといわざるを得ない。また、本件契約における解約金を含む解約予告条項は、借地借家法の規定に反する特約とはいえないから、借地借家法違反をいう原告の主張は理由がない。原告は、本件契約の賃料が高額に過ぎたと主張して、この点を問題とするが、そうであれば、減額請求をすればよいのであり(本件契約には不減額の特約はない。)、また、賃料が減額されれば、解約時の減額された賃料を基に解約金が算定されるのであるから、上記解約予告条項における解約金の定めが賃料減額請求を認める借地借家法の趣旨に反するともいえない。したがって、12か月分の賃料相当額の解約金の支払約定の6か月を超える分が無効であるとする原告の請求は理由がない。
契約締結時の契約書のチェックと交渉が重要
上記で紹介したように、中途解約時の残存期間の賃料相当額の違約金は1年間分程度は有効とされてしまいます。
したがって、契約締結時の契約書のチェックや交渉により違約金条項を削除するよう交渉していく必要があります。
また、1年間分を超える部分が絶対に無効になるわけではないので、仮に1年間分を超える賃料相当額の支払い可能性がある違約金条項がある場合は、少なくとも1年間分を限度とするよう交渉しましょう。