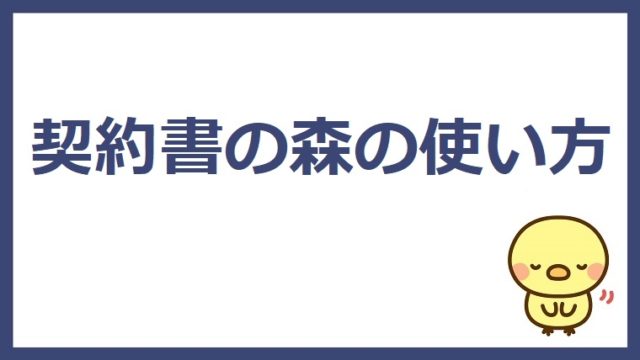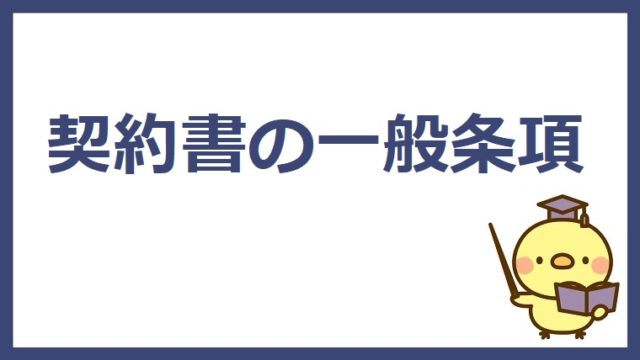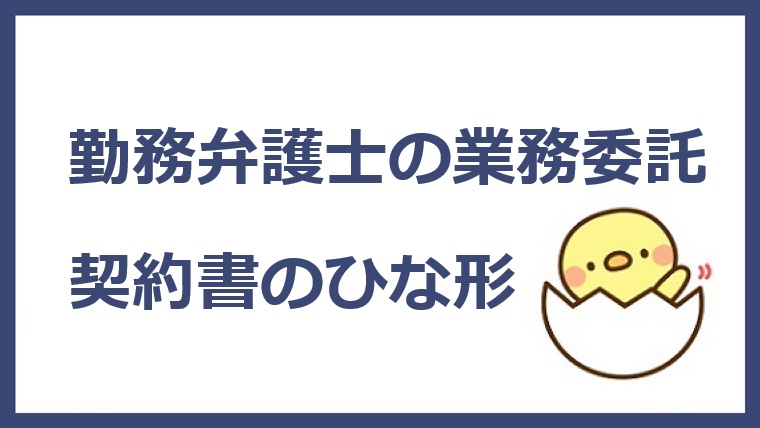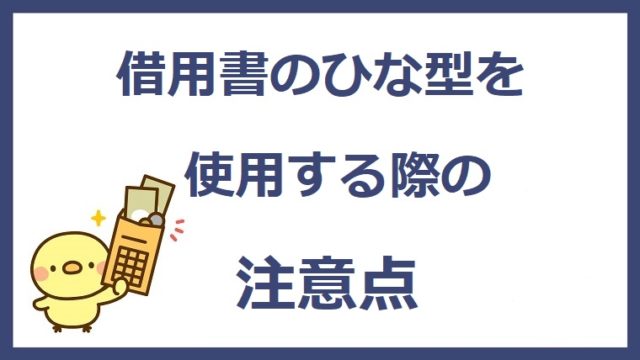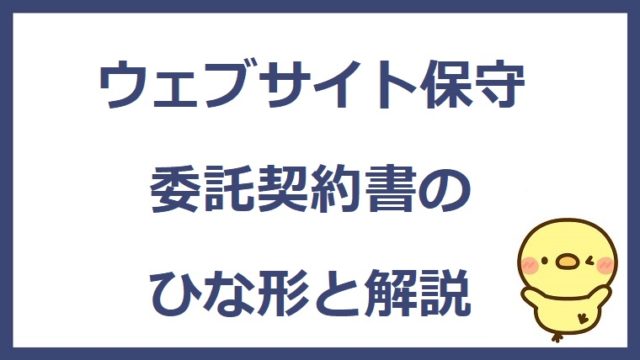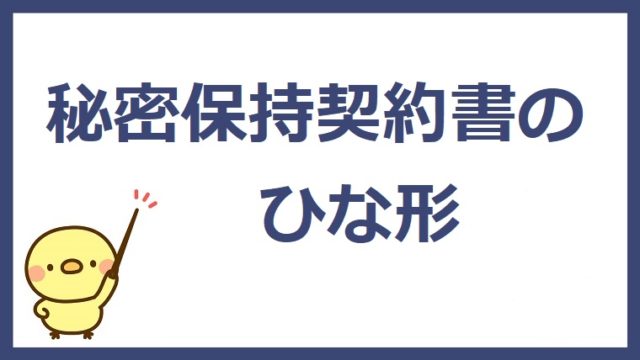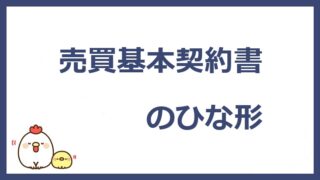法律事務所と勤務弁護士の契約形態
法律事務所の勤務弁護士(いわゆるイソ弁)との契約形態には、業務委託契約と雇用契約があります。
従来は、業務委託契約が多数でしたが、最近は社会保険の適用や安定性を志向する勤務弁護士が増えているため、雇用契約が増えつつあります。
とはいっても伝統的な法律事務所を中心にまだまだ業務委託契約が主流です。各法律事務所の業務委託契約の内容はブラックボックスみたいなところがあり、一般的に公開はされていません。そもそも契約書をきちんと締結しているというところもこれまで少なかったのではないかと思います。
しかし、2024年11月1日からのフリーランス新法の施行により、「契約は口頭で」とは言ってられなくなりました。多くの場合、勤務弁護士はフリーランス新法上の「特定受託事業者」に該当し、法律事務所側(ボス弁側)は「業務委託事業者」、「特定業務委託事業者」に該当すると考えられます。
そのため、法律事務所側は、取引条件の書面等による明示義務を負うことになり(フリーランス新法3条)、対応としては契約書を作成することになります。
毎年、相当数の勤務弁護士の業務委託契約書が作成されることになりますが、これのひな形等が収録された文献等は見たことがありません。
※日弁連の会員ページにはいくつかの書式があります。
そこで、個人事業主の法律事務所経営者と勤務弁護士との業務委託契約書案を作ってみました。内容的には、個人事件可、個人事件の経費分担有の内容で作っています。
業務委託契約書作成の注意点
労働者性
一般的な勤務弁護士の労働者性は否定されるケースが多いと考えられますが(横浜地方裁判所川崎支部判決令和3年4月27日)、契約内容や実態によっては労働者性が肯定される可能性があります。
勤務弁護士の労働者性が肯定された場合、各種の労働法規違反の指摘や時間外割増賃金の請求を受けるおそれがあります。
業務委託契約の内容や実態としても、使用従属性があると判断されないように注意が必要です。
取引条件の明示
フリーランス新法に対応するため、契約書で取引条件を明示する場合は、以下の内容を含めておく必要があります。
- 給付の内容
- 報酬の額
- 支払期日
- 業務委託事業者・フリーランスの名称
- 業務委託をした日
- 給付を受領する日/役務の提供を受ける日
- 給付を受領する場所/役務の提供を受ける場所
- (検査をする場合)検査完了日
- (現金以外の方法で報酬を支払う場合)報酬の支払方法に関して必要な事項
勤務弁護士の業務委託契約書のひな形
業務委託契約書
弁護士____(以下「委託者」という。)と弁護士____(以下「受託者」という。)は、委託者が受託者に対し、法律事務等を委託するにあたって、次のとおり業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(委託業務の内容、対価)
受託者は、委託者の法律事務所(以下「当事務所」という。)に所属の上、以下の業務を受託する(以下「本業務」という。)。
業務内容:当事務所が受託した法律事件・法律事務の処理、当事務所の運営に関わる事務等
報酬:月額 円(税抜)
2.本業務は、当事務所で行うことを原則とし、必要に応じて裁判所、依頼者方等、適宜の場所で行う。
【業務内容と対価を定めた条項です。事務所によっては、歩合の制度を定める場合もあります。】
第2条(支払方法)
委託者は、本業務の委託料を、毎月末日限り受託者の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は委託者の負担とする。
【報酬は役務の提供を受けた日から60日以内に支払う必要があります(フリーランス新法4条1項)。】
第3条(費用負担)
本業務の処理に要する以下の費用は委託者の負担とする。
(1)本業務の処理に必要な当事務所からの交通費
(2)本業務の処理に必要な印刷、郵送等の事務にかかる費用
(3)当事務所指定のメールアドレス、ソフトウェア等にかかる費用
(4)当事務所の固定電話回線、専有の事務室の通信回線、執務スペース、PC等の設備にかかる費用
(5)弁護士賠償責任保険の保険料
2.以下の費用は受託者の負担とする。
(1)受託者の弁護士会費
(2)受託者の自宅等から当事務所への交通費
(3)受託者の携帯電話の端末、同端末の回線、専有の事務室外における通信回線(モバイルWiFi等)にかかる費用
(4)受託者の判断で、受託者名義で契約したクラウドサービス、ソフトウェア等にかかる費用
(5)受託者の判断で加入した弁護士会の会派、弁護団、研究会等の年会費等
3.受託者は、第1項の費用について自ら負担した場合は、毎月末日締で第1条の報酬の請求と併せて委託者に請求し、委託者は翌月末日限り、第1条の報酬と併せて受託者に支払う。
【弁護士会費の負担など、事務所によって経費の負担が異なると思われますので、実態に合わせて経費の負担関係を明確にする必要があります。また、この負担関係は労働者性の認定にも影響しうる要素です。】
第4条(個人事件)
受託者は、本契約期間中、自己の名義及び責任に基づき、弁護士業務を受任することができる(以下、受託者が受任した事件及び事務を「個人事件」という。)。
2.受託者は、個人事件を受任するにあたっては、委任状、委任契約書等に個人事件であることを明記するなどし、依頼者に事務所事件であると誤認させないよう適切な措置をとらなければならない。
3.受託者は個人事件の業務遂行にあたり、当事務所の設備、スタッフ(非弁護士の従業員)を使用することができる。
4.受託者は、個人事件の売上について、以下のとおり経費分担金を、毎月末日締翌月末日限り、委託者の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は委託者の負担とする。
(1)契約期間中の個人事件の売上金額(実入金額、税抜)が___万円以下の部分
売上金額(実入金額、税抜)の30%(税抜)
(2)契約期間中の個人事件の売上金額(実入金額、税抜)が___万円超の部分
売上金額(実入金額、税抜)の20%(税抜)
(3)前二号の売上金額には着手金、事務手数料、報酬金、各種手数料を含むが、個人事件の処理に要した実費にかかる売上金額は含まない。ただし、当該実費を当事務所が負担した場合は、当該実費全額を経費分担金として、受託者は委託者に支払うものとする。
ただし書きの例)受託者が個人事件の処理に当事務所のレターパック・切手等を使用した際、受託者が顧客に当該レターパック・切手等の実費の支払いを受けたとき等
(4)弁護士としての地位に基づき支払われる報酬等(社外役員、大学等の実務家教員、弁護士会の会務、講師、執筆等に対して支払われる報酬等)は原則として個人事件の売上金額とみなすが、該当性については適宜協議の上決定する。
(5)弁護士の職務に関連しない報酬等は、個人事件の売上金額とはしない。
※例)投資による収入、収益不動産の家賃収入、弁護士業務に関連しないアルバイト等の収入等
5.受託者は以下の事件については、個人事件として受任することはできない。
(1)当事務所の依頼者(潜在的な依頼者を含む。)を相手方とする事件
(2)悪質商法、情報商材、アダルト関連事業者、反社会的勢力関係者等を依頼者とする事件
(3)受任することが弁護士法または弁護士職務基本規程に違反する事件
(4)合理的な理由により、委託者が受任を不適切と判断した事件
6.受託者は、個人事件の処理について、委託者に助言、指導等を求めることができる。
7.受託者は、前各項によるほか、委託者の承諾を得た上で、当事務所の事件として、委託者に事件の共同受任を打診することができる。この場合、受託者が事件処理の一部を担当する場合は、受託者の負担等を考慮の上、委託者は、受託者に第1条の報酬とは別に相当額の報酬を支払う。
8.受託者は、個人事件の広告は、事前に委託者の承諾を得て行うものとし、広告にあたっては、弁護士等の業務広告に関する規程を厳守し、当事務所及び弁護士の品位を害してはならない。
【個人事件に関する規律を定めた条項です。個人事件を一切禁止とすると労働者性が認定されやすくなると考えられます。】
第5条(厳守事項)
受託者は、本業務及び個人事件を遂行する上で、弁護士法、弁護士職務基本規程、弁護士会の規則、当事務所の規則等を厳守しなければならない。
2.受託者は、本業務を遂行するにあたっては、委託者の貸与するPCを使用するものとし、委託者の承諾なく貸与PCを目的外に使用してはならない。ただし、受託者は、貸与PCを弁護士会の会務及び個人事件の遂行に使用することができ、また、委託者の承諾を得た上で、PCの貸与を受けず、自ら用意したPC等のデバイスを使用することができる。
第6条(知的財産権)
本業務により受託者が制作した成果物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)等の知的財産権は委託者に帰属するものとし、受託者は著作者人格権を行使しない。
2.前項の対価は、第1条の報酬に含まれるものとする。
第7条(秘密保持)
受託者は、委託者の承諾なくして、本契約に関連し営業上または技術上の秘密情報(以下「秘密情報」という。)を、第三者に対して開示、漏洩してはならず、本契約の履行以外の目的で使用してはならない。ただし、以下のいずれかに該当する情報は秘密情報には含まれない。
(1)開示された時点において、既に公知であった情報
(2)開示された後に受託者の責任によらないで公知になった情報
(3)開示された時点において、受託者が既に了知していた情報
(4)正当な権限を有する第三者から、受託者が秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
2.当事務所の依頼者に関する情報は秘密情報とみなす。
3.受託者は、本契約終了後、秘密情報が記録された媒体を、委託者の請求により委託者の指定する方法で返還または廃棄しなければならない。
第8条(権利義務の譲渡等の禁止)
委託者及び受託者は、あらかじめ書面により相手方の承諾を得なければ、本契約上の権利義務ならびに本契約上の地位を、第三者に譲渡、移転その他の方法により処分してはならない。
第9条(解除)
委託者及び受託者は、相手方が本契約に違反したときは、相当の期間を定めた催告をし、催告期間が終了しても違反が是正されない場合、本契約を解除できる。
2.委託者及び受託者は、相手方に次の各号いずれかに該当する事由が生じたときは、何らの催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1)本契約の違反が重大なとき
(2)弁護士会への懲戒請求が懲戒委員会の審査に付されたとき
(3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあったとき
(4)差押え、仮差押え等の強制執行、または公租公課の滞納処分を受けたとき
(5)支払停止、または支払い不能に陥ったとき、若しくは手形が不渡となったとき
3.前二項の定めにより本契約が解除された場合でも、解除権を行使した当事者は損害賠償の請求を妨げられない。
第10条(反社会的勢力の排除)
委託者及び受託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、その他これに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2.委託者及び受託者は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、ただちに本契約を解除することができ、解除により相手方に損害が生じてもこれを賠償することを要しない。
(1)相手方または相手方の役員が反社会的勢力に該当すると認められるとき
(2)相手方の経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
(3)相手方が反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4)相手方が反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5)相手方または相手方の役員もしくは相手方の経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6)自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用毀損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき
3.委託者及び受託者は、自己が前項各号に該当したため相手方が本契約を解除した場合、相手方に生じた損害を賠償しなければならない。
第11条(有効期間)
本契約は、20__年__月__日から1年間有効とし、期間満了の3か月前までに更新及び更新後の契約条件について委託者及び受託者は協議するものとする。
2.前項の定めにかかわらず3か月前に通知することで、委託者及び受託者は本契約を中途解約することができる。
3.第6条(知的財産権)、第7条(秘密保持)、第12条(管轄)の規定は、本契約の終了後も有効に存続する。
【自動更新としてもよいですが、毎年契約条件を更改する事務所が多いのではないかと思います。】
第12条(管轄)
本契約に関する一切の紛争は、___地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第13条(協議事項)
本契約に定めのない事項、ならびに本契約の解釈について疑義を生じたときは、当事者間で誠実に協議のうえ解決する。
第14条(特約事項)
第4条の経費分担金の上限を本契約期間有効期間中、実費分を除き___万円(税抜)とする。
本契約の締結を証するため、本書を2通作成し、委託者及び受託者記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
20__年__月__日
(委託者)
(受託者)